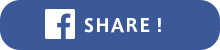つながる脳科学
「心のしくみ」に迫る脳研究の最前線

理化学研究所 脳科学総合研究センター編
利根川 進 ほか
講談社
ものごとを考え、記憶し、日々の出来事に感情を揺さぶられる…。
謎めいていた脳のはたらきが、明らかになりつつある。
グリア細胞とニューロン、進化と可塑性、場所細胞と空間記憶、情動と消去学習、海馬と扁桃体とエングラムセオリー。
頭の中には、さまざまな「つながり」があった!?
9つの最新研究から、心を生み出す脳に迫る!Kindle版も購入可能。
ここまでわかった! 脳とこころ
こころの科学増刊

加藤 忠史編
日本評論社
理化学研究所 脳科学総合研究センター設立20周年記念。脳科学研究の最前線はどうなっているのか。日本の第一人者たちが明かす、脳とこころ、そしてこころの病気のこれまでとこれから。
アルツハイマー病は治せる、予防できる

西道 隆臣
集英社
超高齢化社会へひた走る日本。認知症高齢者の数は今や約462万人と推計されており、2025年には700万人を超えるという。その認知症のうち約60%を占めるとされるのがアルツハイマー病だが、根本的な治療薬はいまだ存在しない。
しかし、理化学研究所のプロジェクトチームが、アルツハイマー病の原因物質であるアミロイドβを分解する酵素「ネプリライシン」を発見。同病の治療・予防に大きく道を開いた。
同プロジェクトのリーダーである研究者が、アルツハイマー病治療をめぐる最新の研究成果を明らかにする。
脳・心・人工知能
数理で脳を解き明かす

甘利 俊一
講談社
数理で「脳」と「心」がここまでわかった!
囲碁や将棋で、AIが人間に勝利を遂げた。
2045年、人工知能が人間の能力を超える「シンギュラリティ」は、本当に訪れるのか?
数学の理論で脳の仕組みを解き明かせれば、ロボットが心を持つことも可能になるのだろうか?
AI研究の基礎となった「数理脳科学」の第一人者が語る、不思議で魅惑的な脳の世界。
つながる脳科学
「心のしくみ」に迫る脳研究の最前線

理化学研究所 脳科学総合研究センター編
利根川 進 ほか
講談社
ものごとを考え、記憶し、日々の出来事に感情を揺さぶられる…。
謎めいていた脳のはたらきが、明らかになりつつある。
グリア細胞とニューロン、進化と可塑性、場所細胞と空間記憶、情動と消去学習、海馬と扁桃体とエングラムセオリー。
頭の中には、さまざまな「つながり」があった!?
9つの最新研究から、心を生み出す脳に迫る!Kindle版も購入可能。
ここまでわかった! 脳とこころ
こころの科学増刊

加藤 忠史 編
日本評論社
理化学研究所 脳科学総合研究センター設立20周年記念。脳科学研究の最前線はどうなっているのか。日本の第一人者たちが明かす、脳とこころ、そしてこころの病気のこれまでとこれから。
精神と物質
分子生物学はどこまで生命の謎を解けるか

立花 隆、利根川 進
文藝春秋
ノーベル生理・医学賞受賞の利根川進氏との20時間に及ぶ徹底インタビューを通して、生命科学の最先端の現状をわかり易く解説する。
私の脳科学講義

利根川 進
岩波書店
抗体の多様性の謎を解明してノーベル賞を受賞した利根川博士は、いま世界の脳研究をリードする。脳にためた記憶を取り出すプロセスをはじめとする自らの研究成果を通して、脳科学の最先端と何を明らかにしてきたのかを紹介する。目的・戦術・技術がみごとに組み合わさったその研究手法には目を見張らされる。
脳研究の最前線(上巻)

理化学研究所脳科学総合研究センター
講談社
「脳科学総合研究センターが創立10周年を迎えるにあたって、『脳とこころ』の問題についての現在もっとも進んだ理解を示そうと企画されたのが本書である。現代の脳科学には脳とこころの問題に切り込むためのいくつかの重要な手掛かりがある。…12名の研究者がそれぞれに描く『こころに向かう脳科学』の流れと将来の大きな展望を読者に読み取っていただければ幸いである」――(伊藤正男)
脳研究の最前線(下巻)

理化学研究所脳科学総合研究センター
講談社
「調べてみればみるほど、脳は複雑である。その仕組みを知るためには、ゲノムからはじまり、分子の働き、細胞、ネットワーク、さらに情報へと進んでいかなくてはいけない。また、精神疾患など、脳の働きの障害も大変な問題である。技術応用に関しては、脳の仕組みを取り入れたロボットの開発に皆の目が注がれている。もちろん、心の仕組みを理解することが究極のターゲットである」――(甘利俊一)
脳科学の教科書 神経編

理化学研究所脳科学総合研究センター(編集)吉原 良浩、入來 篤史、加藤 忠史
岩波書店
脳で人間のすべてがわかる!?テレビを観ているとそんな気がしてきますが、本当のところ、どこまでが解明され、なにが謎のままなのでしょうか。たしかな入門書を読んで、正しい知識を得、自分で考える力を身につけませんか。ちまたの情報のウソ・ホントや、最近の研究成果を解説するコラムもついて、読み応え満点です。
脳科学の教科書 こころ編

理化学研究所脳科学総合研究センター(編集)加藤 忠史、入來 篤史
岩波書店
こころは脳のはたらきであることは、ご存じですね。では、脳のどこで、どんな感情が生みだされるのでしょうか? ヒトに特有の象徴的世界をつくりだすことばは、どこで生みだされるのでしょうか? それらについてわかっていること、さらに脳機能を調べる手段としての画像法、神経疾患・精神疾患と脳とのかかわりも解説します。
育つ・学ぶ・癒す
脳図鑑21

序文 伊藤 正男
工作舎
技術の進歩によって、環境とダイナミックに連動する脳の姿が明らかになってきた。一体、脳はどのようになろうとしているのか? 第一線で活躍する研究者41名の執筆陣と豊富なイラスト資料で構成する、最新版「脳」ビジュアル大全。
いのちの持続、スポーツ、読書、創造活動、脳型コンピュータ、自己治癒…最新の脳研究の成果を集成。
脳を知る・創る・守る

伊藤 正男
クバプロ
現在の脳の研究には、物質科学的な流れと、情報科学的な流れの二つの大きな潮流があります。物質科学の流れは、分子神経科学、細胞神経科学、発達神経科学の三つの分野にわかれ、脳のなかで細胞がどのような分子を駆使して働くか、遺伝子の情報にしたがって脳の複雑な組織ができあがる複雑な物質過程の詳細を明らかにしつつあります。
脳を知る・創る・守る(2)

伊藤 正男
クバプロ
「脳の世紀」という言葉には、21世紀は脳の世紀だという私どもの強い想いが表現されています。現在、いろいろな学問分野が興隆してきています。生命科学とかライフサイエンスと呼ばれる分野が今世紀後半急速に発展し、次の世紀にもおおいに栄えると思われます。
脳を知る・創る・守る(3)

伊藤 正男
クバプロ
脳の研究は、本書の内容にも象徴されているように多彩な内容を含んでいます。自然科学としては、原理的な興味の深い領域で、これまで多くの努力が重ねられてきたにもかかわらず、まだ中心に大きな謎が残されています。
脳を知る・創る・守る(4)

伊藤 正男、御子 柴克彦、深井 朋樹 ほか
クバプロ
われわれが三次元を認識するメカニズムについて考えてみます。それには頭頂葉が重要な働きを担になっていますが、そのなかでどのような神経細胞が、空間のどのような側面を認知するのかということが、少しずつ明らかになってきました。
脳を知る・創る・守る・育む(5)

伊藤 正男、津本 忠治ほか
クバプロ
「脳の世紀」活動10年目にあたって、これまでの研究成果とこれからの研究の展望を語る。脳の臨界期のメカニズムからヒューマノイドロボットの可能性まで幅広い内容を収録
脳を知る・創る・守る・育む(6)

伊藤 正男、森 憲作、ヘンシュ 貴雄
クバプロ
脳の発達、認知能力の研究、さらにはよりヒトに近いロボットの制作は可能なのかなど多彩な内容を盛り込んだ。脳疾患の治療の展望も含む。特別講演は、作家の加賀乙彦。
脳の中身が見えてきた

甘利 俊一、利根川 進、伊藤 正男
岩波書店
記憶や学習をはじめとした脳の働きが、遺伝子の言葉で語れるようになってきました。人は物事をどのように学び、どう利用していくのでしょうか。こうした活動に関係する物質が明らかにされつつあります。それらが、脳の回路網や、その制御の仕組みとどう関係しているのか。当代を代表する3人の脳科学者が、やさしく語ります。
脳科学のテーブル

甘利 俊一 ほか
京都大学学術出版会
人間はどこまで「脳」の謎に迫れるのか?世界の研究をリードした重鎮と第一線の研究者が、未知の世界へ踏み込んだ先人たちの業績を振り返り、研究史を切り開いた諸概念と近未来のテーマを闊達に語る。最先端の巨大科学となった研究も、人の営みの積み重ねによって展開していく。科学と科学者のあり方を、研究者自身の体験から生き生きと描き出すことで、過去から現在、未来へと見渡す脳研究の鳥瞰図。
ハダカデバネズミ
女王・兵隊・ふとん係

吉田 重人、岡ノ谷 一夫
岩波書店
ひどい名前、キョーレツな姿、女王君臨の階級社会。
動物園で人気急上昇中の珍獣・ハダカデバネズミと、その動物で一旗あげようともくろんだ研究者たちの、「こんなくらしもあったのか」的ミラクルワールド。
なぜ裸なの? 女王は幸せ? ふとん係って何ですか?
人気イラストレーター・べつやくれい氏のキュートなイラストも必見!
アルツハイマー病は治せる、予防できる

西道 隆臣
集英社
超高齢化社会へひた走る日本。認知症高齢者の数は今や約462万人と推計されており、2025年には700万人を超えるという。その認知症のうち約60%を占めるとされるのがアルツハイマー病だが、根本的な治療薬はいまだ存在しない。
しかし、理化学研究所のプロジェクトチームが、アルツハイマー病の原因物質であるアミロイドβを分解する酵素「ネプリライシン」を発見。同病の治療・予防に大きく道を開いた。
同プロジェクトのリーダーである研究者が、アルツハイマー病治療をめぐる最新の研究成果を明らかにする。
アルツハイマー病の早期診断と治療
脳を知る・創る・守る・育む15

伊藤 正男、黒田 公美、津本 忠治 ほか
クバプロ
2013年の脳の世紀シンポジウムをまとめた収録集。
特別講演は、NPO法人脳の世紀推進会議理事長の伊藤正男氏。
脳と精神疾患

加藤 忠史、津本 忠治
朝倉書店
うつ病などの精神疾患が現代社会に与える影響は無視できない。本書は,代表的な精神疾患の脳科学における知見を平易に解説する。〔内容〕統合失調症/うつ病/双極性障害/自閉症とAD/HD/不安障害・身体表現性障害/動物モデル/他
うつ病の脳科学
精神科医療の未来を切り拓く

加藤 忠史
幻冬舎
日本のうつ病等の気分障害患者が90万人を超えた。だが、病因が解明されていないため、今のところ処方薬も治療法も手探りの状態にならざるを得ない。一方、最新の脳科学で、うつには脳の病変や遺伝子が関係することがわかった。うつの原因さえ特定できれば、治療法が確立できる。今こそ、最先端脳科学と精神医学を結びつける研究環境が必要だ。うつ研究と脳科学の世界最新情報から、今後、日本がとるべき道までを示した、うつ病診療の未来を照らす希望の書。
脳科学エッセンシャル
精神疾患の生物学的理解のために

加藤 忠史 ほか
中山書店
脳科学研究の進歩は著しいものがあり、精神医学の進歩も脳科学に負うところが大きくなっています。本巻は、精神科医に向けて簡明に書かれた脳科学の書として、最先端の脳科学研究のエッセンスを幅広く集約し、イラストを多用して視覚的に理解しやすくしたものです。 脳から回路、そして分子へと脳を俯瞰した脳科学の入門書です。
岐路に立つ精神医学
精神疾患解明へのロードマップ

加藤 忠史
勁草書房
50年ほど前から画期的な進歩がない精神疾患治療。ゲノムや脳の研究を組み合わせて疾患の原因を解明し、根本的な治療法、診断法を開発することによって、精神科医療にイノベーションをもたらすことはできるのだろうか。精神医学が直面する困難を乗り越え、真の医学として発展していくために、我々は今何をしたらよいのかを問い直す。
動物に「うつ」はあるのか
「心の病」がなくなる日

加藤 忠史
PHP研究所
動物にも精神疾患はあるのか?―この疑問は、そもそも「心の病」とは何か、私たち人類はどうすればこれを克服できるのかという社会問題そのものである。毎年三万人が自殺で亡くなり、休職者の激増が取り沙汰されながら、じつは根本的な原因も確実な診断法や治療法もわかっていない精神科医療の実情。ただ話を聞いて「とりあえず抗うつ薬」では、真の問題解決にはならない。ひょっとしてうちのイヌ、うつ病!?何も語らない動物を通して、「悩み」と「病気」の線引きの難しさ、心と脳をつなぐ研究の最新動向を読み解く。
脳(ブレイン)バンク
精神疾患の謎を解くために

加藤 忠史
光文社
統合失調症、うつ病、双極性障害、依存症を根本から治すには? 精神疾患における最先端の研究事例を紹介し、乗り越えるべき最後の壁――脳を直接調べることの必要性を解く。
精神の脳科学(シリーズ脳科学 6)

甘利 俊一、加藤 忠史
東京大学出版会
脳科学のさまざまなアプローチのなかで、精神の病態である精神疾患の研究は、分子レベルでの研究と脳画像研究や心理・行動のレベルでの研究をつなげ、統一的理解を可能にしうるものの一つである。現在急速に進展しつつある精神疾患の脳科学研究の最前線。
認識と行動の脳科学(シリーズ脳科学 2)

甘利 俊一、田中 啓治
東京大学出版会
知覚認識、記憶、行動の制御などは、いかに行われているのか。本書は、人間が通常意識せずに行っているこのような脳の活動を、システム・神経回路・神経細胞・シナプスの働きとして理解し、解説。誰しもが興味をもつ題材をシステム脳科学の視点から捉える。
脳の発生と発達(シリーズ脳科学 4)

甘利 俊一、岡本 仁
東京大学出版会
本書は、2つの異なるタイムスケール、億年単位で起こる進化の観点と、数時間から数ヵ月で起こる発生の観点から、脳の成り立ちを論じる。神経発生生物学の基礎から再生医学への可能性などまで、従来の神経科学の枠組みにも挑戦する野心的な一冊。
分子・細胞・シナプスからみる脳(シリーズ脳科学 5)

甘利 俊一、古市 貞一
東京大学出版会
脳は体の代謝から、情動、記憶、学習までをも制御する高度な情報処理器官である。この基盤となる分子、細胞やシナプスの研究を、その基礎から、ゲノム・エピジェネティクスといった最新の研究成果まで含めて、はじめて体系的に解説した決定版テキスト。
恋う・癒す・究める
脳科学と芸術

岡ノ谷 一夫、入來 篤史、藤井 直敬ほか
工作舎
複雑な歌をうたおうと練習にいそしむ小鳥、アクションペインティングさながら夢中で絵を描くチンパンジー、2万年余にわたり、洞窟の暗闇にみごとな絵を描いてきた私たちの先祖…。なぜ美しいものに魅了されるのか?失語症になっても歌ならうたえるのはなぜか?脳の病がもたらす芸術的表現とは?左手がひらいた新たな音楽的境地とは?能の秘伝に託された身体芸術の極意とは?生物研究や乳幼児の発達の観察、リハビリテーションの現場での知見、認知科学や脳神経科学などの最先端の成果と、アートシーンの最前線における体験的考察により時代や地域性を超える力をもつ芸術の妙をあかす。
言葉はなぜ生まれたのか

岡ノ谷 一夫
文藝春秋
ジュウシマツの歌には文法があり、ハダカデバネズミは鳴き声で上下関係を確認。人間の「ことば」の誕生の謎を楽しみながら学べる本。
動物は「鳴き声」を出せるけれど、「言葉」を話すことはできません。頭のいいチンパンジーでさえ、それは無理なのです。なぜ人間だけが言葉をもつようになったのでしょう。
さえずり言語起源論
新版 小鳥の歌からヒトの言葉へ

岡ノ谷 一夫
岩波書店
ジュウシマツの歌には「文法」がある――これが転機をもたらす大発見だった。進化的な起源の異なる小鳥の歌が言語進化の謎に迫るカギとなるのはなぜなのか。初版刊行から七年半を経て性淘汰起源説に相互分節化仮説が加わった。「言語の起源は求愛の歌だった」とする進化のシナリオを、苦労・喜び・興奮満載の研究者人生とともに描く。
「つながり」の進化生物学

岡ノ谷 一夫
朝日出版社
歌う動物、言葉をもったヒト。媚びを売るメス鳥?言葉をまねるゾウ?小鳥も赤ちゃんも、「文法の種」をもっている。高校生と考える、コミュニケーションの起源とこれから。
言葉の誕生を科学する

小川 洋子、岡ノ谷 一夫
河出書房新社
人間が“言葉"を生み出した謎に、科学はどこまで迫れるのか? 鳥のさえずり、クジラの鳴き声……言葉の原型をもとめて人類以前に遡り、人気作家と気鋭の科学者が、言語誕生の瞬間を探る!
〈神経心理学コレクション〉Homo faber
道具を使うサル

入來 篤史
医学書院
二足歩行や火の使用とともに、道具の使用はヒトと動物を分つ指標であった。
本書は道具使用をニホンザルで研究してきた気鋭の生理学者が書下ろした世界で最初の「ホモ・ファベル(工作人)」論。
内容は生物進化から分子遺伝学と多岐にわたり、ダイナミックな道具論を展開するとともに、著者の絶えざる思考実験の軌跡とサイエンティストの遊び心が感じられる。
言語と身体性

入來 篤史 ほか
岩波書店
人間は、なぜ言語以前の身体の知覚や感情を言語という記号に結びつけられるようになったのか。そもそも音声言語の進化的基盤はどこにあるのか。子どもの言語獲得や意図理解はどのように発達するのか。手話やジェスチャーはどのように生成されるのか。実験観察や計算モデルなどの手法を取り入れ、いわゆる「記号接地問題」を解く。
共感

入來 篤史 ほか
岩波書店
現代のコミュニケーションにおいて、なぜ「共感」に焦点を当てる必要があるのか。そもそも「共感とは何か」をこれまでの研究史をたどりながら定義し、その生起メカニズムを考える。とくに感情の伝染、共感の意識性、共感の身体反応、内受容感覚、共感の発達と病理などについて、心理・脳・身体という三つの側面から幅広く検討する。
母性と社会性の起源

入來 篤史 ほか
岩波書店
「育てる」「真似る」「教える」「騙す」「伝える」といった他者との相互作用の進化的基盤はどこにあるのか。脳のどのような作用がそれを生むのか。自己・他者の関係の原点である母子関係から出発し、人の知性や社会性の獲得にいたるしくみを、赤ちゃん学や動物学・ロボット学の成果を通して明らかにし、研究の方向性を示す。
社会のなかの共存

入來 篤史 ほか
岩波書店
なぜわれわれは他人の目を意識するのか。正義やモラルは生得的なものなのか。多数の人間が共存するためのしくみが、動物でもあるヒトの心のしくみとしてどう形づくられるのかを社会科学と生物科学の両面から読み解く。利他・互恵行動や賞罰などの社会制度の源流を探り、安心や信頼の構造がいかにして生まれるかを明らかにする。
自立と支援

入來 篤史 ほか
岩波書店
病気や障害をもつ人びと、あるいは子どもや高齢者への支援は、相手への思いやりや共感が前提である。支援する者とされる者との立場の非対称を踏まえ、自己の尊厳を守り、自己の存在をいかに相手に認めてもらうかが鍵となる。それを可能にするコミュニケーションの特徴とは何か。臨床現場では何が問われているのかを明らかにする。
言語と思考を生む脳(シリーズ脳科学 3)

甘利 俊一、入來 篤史
東京大学出版会
脳のなかで最も高度に発達した機能の一つが、ヒトの言語処理である。ヒトは言語によって思考し、コミュニケーションをとり、社会を形成する。本書は、言語・概念形成を可能にする脳神経メカニズム、またその進化と発達について探るものである。
スポーツと脳
脳を知る・創る・守る・育む16

津本 忠治、下郡 智美ほか
クバプロ
第22回脳の世紀シンポジウムの講演収録集。「スポーツと脳」をテーマに、ハンマー投げの室伏広治氏の特別講演、運動に因んだ各分野からの講演をまとめた、シリーズ16本目。
つながる脳

藤井 直敬
新潮文庫
華やかな「脳」ブームの影で、研究現場は長い停滞期にあった。そもそも脳は単独に観察して評価できるのか。従来の研究前提を疑った著者はより社会性の高い環境下での脳の働きに着目する。そして、2頭のサルの上下関係を手がかりに、脳の「他者とつながりたい」本質をとらえ、更にその中核となる心の姿へと迫る―理研期待の研究者が拓く脳科学の新時代。毎日出版文化賞受賞。
ソーシャルブレインズ入門
<社会脳>って何だろう

藤井 直敬
講談社現代新書
「ソーシャルブレインズ」は、「社会脳」と訳される、いまもっとも注目のキーワードです。
本書は、著者の描いた「ソーシャルブレインズ研究の俯瞰図」であり「脳科学者が何を考えながら研究しているかを率直に綴ったノート」でもあります。やわらかな感性と冴えた知性、そして、毎日出版文化賞(前著『つながる脳』NTT出版)を受賞した魅力的な文章で語る、「新しい脳科学の時代」を告げる入門書です。
拡張する脳

藤井 直敬
新潮社
「人間関係」を、脳はどう捉えるのか? 斬新な脳科学の可能性がここに! 『つながる脳』(毎日出版文化賞受賞)で、脳やコミュニケーション研究に一石を投じた著者が開発した、SRシステム。「現実」と「代替現実」を視覚と聴覚を通じて自在に切り替え、脳のリアルな反応から、目の前の「現実」を検証する。相手との関係性や状況で、脳は認識を次々と拡張していく。あなたの「世界」を大きく変える一冊!
予想脳
Predicting Brains

藤井 直敬
岩波書店
これほど盛んに研究されながら、脳科学は進むべき方向を見失っている。脳のさまざまな側面について蓄積された詳細かつ膨大な知見を統合する大きな枠組みが存在しないからだ。本書はその枠組みとして「予想脳」という概念仮説を導入し、多数の脳が相互に影響を及ぼしあっているという事実をもとに、脳の本質的な理解に迫る。
脳・心・人工知能
数理で脳を解き明かす

甘利 俊一
講談社
数理で「脳」と「心」がここまでわかった!
囲碁や将棋で、AIが人間に勝利を遂げた。
2045年、人工知能が人間の能力を超える「シンギュラリティ」は、本当に訪れるのか?
数学の理論で脳の仕組みを解き明かせれば、ロボットが心を持つことも可能になるのだろうか?
AI研究の基礎となった「数理脳科学」の第一人者が語る、不思議で魅惑的な脳の世界。
脳の計算論(シリーズ脳科学 1)

甘利 俊一、深井 朋樹
東京大学出版会
脳機能の理解のためには、脳を理論的に再構成し、情報処理システムとして働く原理を明らかにしたい。この立場から急速に発展してきたのが計算論的神経科学である。工学的に傾きがちな本分野であるが、本書は生物学的な基盤を踏まえて書かれており、脳科学を学ぶ者必読の書である。
情報理論

甘利 俊一
ちくま学芸文庫
「大数の法則」を押さえれば、情報理論はよくわかる!
シャノン流の情報理論から情報幾何学の基礎まで、本質を明快に解説した入門書。