加藤忠史 BSIチームリーダー 双極性障害における先駆的業績にて塚原仲晃記念賞を受賞
2015年2月2日
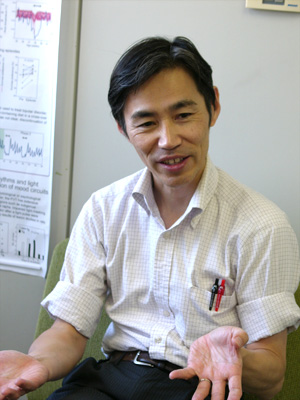
BSI精神疾患動態研究チームの加藤忠史チームリーダーは、精神疾患の神経生物学的基礎を築いた業績により、東京大学の榎本和生博士とともに塚原仲晃記念賞を受賞しました。本賞はサー・ジョン・エックルスの薫陶をうけた神経科学者であり、飛行機事故により1985年に他界した大阪大学の塚原仲晃博士の名を冠した栄誉ある賞で、授与式は2014年9月に横浜で行われた日本神経科学学会にて行われました。
今回、塚原賞受賞を記念し、双極性障害を研究テーマに選んだ理由、ご自身の考える臨床研究と基礎研究の今後、神経科学の将来などについて加藤博士にお話しをうかがいました。
神経科学に関心をもったきっかけとは
高校生のとき、わたしは心理学と精神分析に興味をもち、ジグムント・フロイトの著作を読み、意識、特に夢が果たす役割に関心を寄せました。そこで東京大学医学部に進学したのですが、入学してすぐに、心理学を学ぶことができる部門はないとわかりました。その代り、神経科学では、たとえばREM睡眠中の人の脳活動測定のように、テクノロジーを用いて「こころ(mind)」・意識・前意識について研究できることを知りました。夢さえも神経科学の方法で研究できるだろうとわくわくしながら、「こころ」について学ぶため脳を研究することに決めたのです。
研究の道に進み始めた頃のことを教えてください
神経科学を学ぼうと決めたとき、「こころ」を研究するには臨床研究から入らないといけないと考えました。神経生理学か精神医学かの選択に迷いました。生理学では、神経生理学以外の部分も学ばなければなりませんが、それらはあまり面白そうではなく、精神医学はその全てに興味があったので、精神神経科に入りました。
当時、東京大学では、20年間にわたり精神医学に対する批判的な運動が続いていた頃で、精神疾患の生物学的基盤を東大で研究するのはまだ困難でした。東大病院で1年間臨床研修を行った後、滋賀医科大学の精神科を訪れた際に、分子生物学や生化学、精神薬理学の多くの研究室が精神疾患の生物学的研究を行っていることに驚き、滋賀医科大学に移ることを決めました。
双極性障害の研究に取り組み始めたきっかけ
双極性障害の患者さんを診るにつれ、双極性障害はこころの病気ではなく脳の病気であると確信するようになりました。うつ状態のとき、患者さんは身体を動かすことも会話もできない状態になります。しかし一晩寝ずに過ごした後に突如、興奮・多動の躁状態にかわってしまう。まるで別人のようです。
このような行動の激変にはなにか生物学的現象が潜んでいるに違いないと感じたのです。
当時、分子や細胞レベルで解き明かされた精神疾患はまだなく、診断も心理学的な側面だけでなされていました。一人ひとりの医師が、独自の診断、治療の基準を持っていて、それが医師間でのコミュニケーションを困難にし、精神医学は混乱を極めているように見えました。あたかも、精神医学という学問自体が治療を必要としているかのように感じました。私は、双極性障害の生物学的基盤を同定することこそが、この分野における本当の革新につながると考えました。
日本における双極性障害の診断と治療の進展について
私が研究を始めたころは、統合失調症の研究の方が盛んでした。うつと躁を示す双極性障害の症状はシンプルにみえて、あまり心理学的見地からの興味をもたらさなかったからです。しかし、それまで十分に認識されていませんでしたが、実は、うつや双極性障害のような気分障害がもたらす社会への負担はより大きく、双極性障害の治療への取り組みはより必要とされるものなのです。その仕組みを理解するのが統合失調症と比べて、複雑ではなさそうに感じたこともあって、私は双極性障害をテーマに選びました。双極性障害の原因の一部を同定するのに四半世紀以上も必要であろうことは、そのときは想像もしていませんでした。臨床現場からすると双極性障害の診断方法には大きな進歩がなく、統合失調症と誤診されるケースもまだあるようです。不適切な治療により症状が治まらず、躁・うつを繰り返す患者さんはまだたくさんいるのです。一般の方々と精神科医の双方に対して、双極性障害に関する知識の普及が必要と感じ、その一助として本も執筆することにしました。新しい治療戦略はまだなくとも、精神疾患とそれによる社会的な障害についての誤解や偏見を解き、理解を促進するだけでも、多くの患者さんが救われると考えています。
双極性障害の生物学的基盤に関する研究について
25年前に私が研究の道に入ったときから、双極性障害は細胞内情報伝達の障害とみなされてきました。つまり神経伝達物質に関わる細胞内情報伝達機能の障害という見方です。まだ結論づけられる段階でありませんが、私たちの研究は細胞小器官であるミトコンドリアの機能障害が双極性障害に影響を及ぼすことを示しました。私たちは、双極性障害は単なる情報伝達の機能的な障害ではなく、細胞のより基本的な機能障害に起因するものと考えています。この機能障害が神経細胞自体の死によるのか、樹状突起や軸索の損傷によるのかなどはまだわかっていません。
双極性障害と遺伝の因果関係について
遺伝要因は双子の研究で調べられていますが、まだ原因遺伝子の発見には至っていません。家系の研究でも遺伝子は同定されておらず、現在のところ遺伝は双極性障害のリスク因子のひとつにとどまっています。関連遺伝子の多くは、カルシウムシグナリング、および細胞内でカルシウムを貯蔵している小胞体とミトコンドリアに関わるものです。
(遺伝子により)カルシウム信号がどう影響を受けるかがわかれば、次にカルシウム経路の不具合で細胞はどう影響をうけるのか、研究を進めることができます。このためには脳のどの領域で、どのタイプの細胞が双極性障害で特に影響を受けるかを見いださなければなりません。パーキンソン病も小胞体とミトコンドリアの機能不全で起こる場合がありますが、この機能不全が黒質ドーパミン細胞で起きることが知られています。同様に、双極性障害で機能不全が起きている場所を特定する必要があります。今現在適用できるあらゆる神経科学の技術をもってしても、双極性障害の生物学的原因を同定することはそう簡単ではないでしょう。

先駆的研究に対する塚原仲晃記念賞授与についての感想
大学生のころ塚原先生の書かれた教科書で神経可塑性と記憶について勉強しました。私も51歳となり、先生が飛行機事故で亡くなられた当時と同じ年齢となりました。しかし塚原先生と同じ域に達したかというとまだまだです。受賞された方々をみるとまだ先達のレベルにはほど遠いと忸怩たる思いです。今回、私の過去の業績に対してというよりは、精神疾患の重要性を理解いただき、研究の難しさにも関わらずこの領域の研究を続け、精神疾患の研究を発展させるように、との励ましの意味でこの賞をいただいたものと理解しています。
精神疾患研究のこれからについて
自然科学は動物を含む物質を、社会科学は人々により構成される社会を研究しています。神経科学はこの二つの間にあります。物理化学の技術を用い、人間の行いと社会を理解しようとするのが脳科学研究です。脳科学は生物学の一分野なのではなく、それ一つで独自の領域です。脳科学には3つのゴールがあると考えています。①脳を理解すること、②脳を守ること、③脳を創ること-あるいはブレインマシンインターフェースのように、脳をつなぐことです。私はこのうち精神疾患の理解に注力していますが、そのなかで疾患を観察し記述する臨床医学と、マウスなど実験動物を使って疾患の原因を探る基礎科学の間のギャップを痛感しています。振り返ると、私は大学で双極性障害の臨床研究を12年間、理研BSIで基礎科学研究を14年行ってきました。その観点から、基礎科学と臨床科学の融合が、人間の精神神経疾患を理解するために不可欠であることを示したいと考えています。これからの20年間に、基礎研究と臨床研究の連携により、脳の暗闇を照らす研究が進むと思います。
Interview by Ray Luo
Photo credits: BSPO
© RIKEN BSI 2015