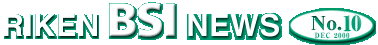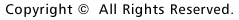|
立花──設立からちょうど3年ですね。私が前回伊藤先生を取材させていただいたときには、まだ国際フロンティア研究システム(*1)のころでした。
伊藤──最初は、国際フロンティア研究システムの中に、脳科学関係の研究室を三つつくって始めたんです。だんだん増やして10年間で10にした。3年前にさらに10チーム増やして20チームで脳科学総合研究センターがスタートしました。それが現在37チームにまで増えました。
立花──3年前にこの研究センターをつくるとき、そもそもどういう研究センターにしようと考えていたのですか。

伊藤正男
BSI所長。1928年生まれ。1953年東京大学医学部卒業。医学博士。1959年、オーストラリア国立大学に留学。シナプスの研究でノーベル賞を受賞したエックルス教授の下で研究を行う。小脳研究の国際的な権威である。東京大学教授などを経て現職。
|
伊藤──日本で今までできなかったことを、ここでみんなやろうと。
立花──ほう。具体的にはどういうことですか。
伊藤──一つは領域の融合です。脳科学はものすごい複合領域ですよね。複合領域が始まるときに、いつも日本は遅れるんですよ。日本は複合的な、学際的な新しい領域の開拓がものすごく下手です。いつも10年、20年たってからやっと欧米に追いつく。
脳のことをやるには学際的な大きな領域として、あらゆる方向から進めないとだめなんです。それをやるには、今の大学ではほとんど不可能です。それが、この研究センターをつくったいちばん大きな理由ですね。
もう一つは国際化です。この研究センターを始めるときに、外国人を全研究者の30%にするという目標を設定しました。多いときで25%、今は約20%が外国人です。37チームのうち外国人のチームリーダーが6人います。
立花──研究センター全体として、国際化しようという雰囲気がありますよね。会議も英語でするそうですね。
伊藤──それをやらないとだめなんですね。セミナーは全部英語ですし、研究室でもほとんど英語を使っている。
立花──領域融合と国際化。それから何かありますか。
伊藤──研究者が若い。平均年齢が33歳です。いちばん頭のさえるいい時期です。私は「黄金の33歳」と言っています。
アメリカの研究システムが成功した非常に大きな秘けつは、ポスドク(*2)が終わった、日本でいうと大学の研究助手クラスにすごい自由を与えたことです。ポスドクが終わってアシスタントプロフェッサーに採用されると、自分でどんどん研究費をNIH(米国立衛生研究所)に申請します。研究費さえもらえればポスドクを雇って、自前で研究ができます。
|