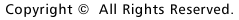|
大阪大学蛋白質研究所において、実学としての学問のとらえ方と自由な雰囲気の中でユニークな発想を要求されながら、実利的な成果
を求めるという環境の洗礼を受け、東京大学医科学研究所へ私は赴任した。同時に理研のライフサイエンス筑波研究センター(当時)で、神経研究の立ち上げを要請され、主任研究員として着任した。筑波の研究室は日本における新しいライフサイエンス研究を目指して井川洋二主任研究員(当時)をはじめとして有能な研究者が、日夜議論を戦わせていた。トップのサイエンスをしなければダメだ、物の考え方は、人材はどうするか、また研究するための研究費はどう集めるか、大変に熱っぽい議論がなされた。
そのうち和光に、これまた日本における画期的な研究体制としてのフロンティア研究システムが発足、伊藤正男先生が着任されその後システム長になられた。脳研究が筑波だけでなく和光にも芽生えはじめ、日本における脳研究への熱い期待と国の予算が連動し、この脳科学総合研究センターが出来ることとなり、伊藤先生が所長として着任した。この実現にあたっては、先日急逝された故小田
稔元理事長をはじめとして多くの方々の御努力によっている。私達も和光へ移り、他のグループと協調して進むこととなった。
理研へ来てから10年目になろうとしているが、理研のすごい点は、強力な事務体制がまず挙げられる。ひとたび決定が行われるとその決定に従って、事務機構が始動する。これは大学機構にはほとんどみられない。また、その議論にしても、かなりドラスティックである。
主任研究員会議での議論の中でも、今後のサイエンスの発展を阻害するものは排除するという方針の下に、自身の体制を破壊するような事であっても実行の方向に向かう。ここまで自分達の権限をなくしても良いかということまで進む。理研の理事会と対決姿勢をとっていたほどの人が何年かすると理事に選出されている。私は理研は本当にすごい、すばらしいところであると思う。
主任研究員会議を中心とした理研の中に、これまでの規模に匹敵するほどの、しかも新しい体制を導入したBSIを認めるところも、やはり理研のすごいところであろう。
さて理研を語る上で高峰譲吉博士を忘れてはならない。最近、飯沼和正、菅野富夫両氏の著作の「高峰譲吉の生涯……アドレナリン発見の真実」(朝日選書)を読む機会に恵まれた。
高峰譲吉博士は化学・薬学に大変秀でた科学者で、タカジアスターゼ、アドレナリンの抽出に成功している。
一方で彼は現在のベンチャービジネスを当時すでに起こし、胃腸薬としての「タカジアスターゼ」と、止血剤や昇圧剤としての「アドレナリン」をパテント化して、巨額の富を得ている。アドレナリンは、世界で最初のホルモン物質であった。
しかも彼は「理化学研究所」の創設を主張し、その設立に貢献している。「独創性」を発揮する人材の育成と独創的な成果
を得るためには官によらない、民間一般に門戸を開いた研究所が必要であるとの信念でその設立を提案し、しかも当時の海軍の最新鋭鑑一隻の建造費に見合う規模のものを国に要求して、理化学研究所が設立された。
高峰博士のベンチャーとしての成功は、彼をとりまく有能な人材に負っている事は確かであるが、彼にはまず実験科学者としての有能性があり、更に優れた先見性と、情報収集力を持ち合わせているなど、やはり高峰博士自身の優れた能力によるのであろう。
学問は素朴な疑問がきっかけで始まるが、自分の興味本位の仕事に留まることが多い。高峰博士は実学としての理化学研究所の考え方を既に確立し、かつ強力に実践していた。
現在の理研は高峰博士の流れを汲みながら、優れた先人の努力により、日本の中でも独特な大きな流れを作っている。その中にあってBSIはさらに自由度、実践性、活動性をもってはばたきつつある。
体制というものは我々その構成員がつくるものであり、見かけ上強固に見えても以外とすぐに破壊してしまうことがある。世界に開かれ、世界に発信する理研BSIから、世界を真にリードする理研BSIへと、多くの有能な人材を集めつつ、大きく成長させたいものである。
|