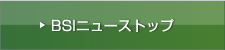はじめに
仏教の教えには「四つの聖なる真実」(苦、集、滅、道)という考えが存在します。 これは、人生は苦であり(苦)、その苦しみの根源は自己愛の渇望(集)から生じるが、その渇望を断ち切れば苦しみも消滅し(滅)、そのための正しい修行の道がある(道)という教えです。 この2つ目の“集”は渇愛:タンハーと呼ばれ、生命の根源的な欲望であり、この欲望を満たすという原動力がなければ、世間との交流や成功するために必要な経験を積むための動機が欠如してしまいます。 しかし、逆に欲望が強すぎると己の人生に苦をもたらしてしまうというわけです。


情動状態と快楽状態
一般的に私たちの心の中に存在する感情は、図1に示すような「情動状態」によって表すことができるでしょう。 われわれの情動状態は、喜び、不安、退屈、怒りといった、多様な構成要素の組み合わせによって成り立っています。これらのひとつに「快楽」と呼ばれる状態があります。 「快楽(hedonic)」という単語には「喜びの、喜びに関わる、または、喜びを特徴とする」という意味があります。言い替えれば、我々の快楽状態とは、その時々に経験する幸福、あるいは不幸の度合いのことです。 では、人間は脳の快楽状態がある程度維持されていれば、渇望しすぎて苦しむことも、向上心を失ってしまうこともなく、幸福に生きることができるのでしょうか? 当ユニットでは、人間の本質に迫るために脳内でのこの快楽のメカニズムに興味を持ち、研究を行っています。
脳内での快楽に関わる因子として、オピオイド・ペプチドがよく知られています(図2)。 我々は最近、これらオピオイド・ペプチドの一つ「ノシセプチン」が脳内で快楽状態にどのように関わっているのかを調べました。 マウスでは特定の場所で快楽となる刺激を与えると、後になってその刺激を求めて快楽を経験した場所へ戻る習性があり、その行動を快楽欲求の指標として利用できることが知られています。 我々は、ノシセプチンの働きを抑えたマウスを用いて解析したところ、未処置のマウスに比べて快楽を経験した場所へ移動する傾向が強く見られることを発見しました(図3)。 これはノシセプチンが快楽欲求を抑制する作用を持つことを示唆しており、過剰な快楽欲求を防ぐメカニズムの存在を示す極めて興味深い結果です。 過剰に快楽を求める状態(=中毒など)を抑制するメカニズムが、本来、脳に自然に備わっているのであれば、このメカニズムを解明することによって薬物中毒などの治療、予防につながることが期待できます。
中毒は薬物だけのことではない
あなたは日々の生活において、何かの依存症になっていませんか?このような問いに対して何かの依存性を認識している人々はごく稀でしょう。しかし、自分では何かに依存しているという自覚はなくても、それを突然奪われてしまった場合に、喪失感を味わうものは少なくないはずです。これは、まさに精神的依存の定義に他なりません。中毒とはこれがわずか一歩進んだもの――奪われたものを取り戻すために行き過ぎてしまう、時によって他の重要なものを犠牲にしてまで取り戻そうとしてしまうことなのです。その意味では、おいしい食物、暖かくて安全な場所、仲間付き合い、社会的な結びつきをはじめとして、我々の人生は「自然な」依存であふれかえっています。その中でも、とりわけ、強迫的摂食、つまり食物に対する依存、中毒には大きな関心が寄せられています。事実、西洋諸国では、いたるところで肥満症が蔓延しており、また1970年代以降、日本においてさえも小児性肥満症が倍増しました。そしてもうすぐ、何らかの形で肥満が関与した病因が死因の第一位になることが予測されています。
肥満の原因は主として、身体活動率の低下と食物の過剰摂取(特に、美味しくて満足感を伴う食物の過剰摂取)です。興味深いことに、われわれは、ノシセプチン受容体を欠いたマウスは甘い食物を避ける、という極めて不自然な行動を見せることを発見しました(図4)。この結果は、薬物によって誘導される快楽欲求だけではなく、動物が本来持ち合わせている「自然な」快楽に対しても、オピオイド・ペプチドが関与していることを示唆するデータです。
動機と報酬の神経化学
快楽を調整する神経回路に対する私たちの理解は、1960年代の「中脳辺縁系ドーパミン経路」として知られている一群の神経単位の発見に、大きな影響を受けています。中脳から生じ、腹側前脳で終結するこの経路は、快楽的な刺激に関する一連の情報を伝える神経束のための主要経路であると考えられています(図5)。これはモルヒネ投与による人工的な快楽の誘導により、中脳辺縁系でのドーパミンの放出が上昇することからも裏付けられています。
前述したように脳内のノシセプチン量を増加させると、快楽欲求が抑制されることから、この時、中脳辺縁系経路でドーパミン放出量が低下していることが予測されます。事実、ノシセプチンの投与量の増加に伴い、ドーパミン放出量が低下しており(図5)、この結果は中脳辺縁系ドーパミンが快楽の根底にあるという長年にわたる仮説に合致します。しかし、興味深いことにノシセプチンを阻害した時には動物の快楽要求が増加するにも関わらず、ドーパミンの放出は増加しないことが我々の研究から明らかになりました。この発見は、快楽への渇望を調節するシステムと、快楽そのものを引き起こすシステムが、分離できる可能性を示唆しています。つまり私たち人間は、実際にそれを味わった時に快楽とは感じられない物事に対して、強い渇望を感じる可能性があるということであり、逆に欲望を感じない物事でも、実際に味わってみると快楽と感じる可能性をも示しています。真偽を確かめるにはこの先多くの研究が必要ですが、このような解釈は、麻薬常用者たちがしばしば「麻薬は欲しいが、実際に麻薬を吸ってもたいした快感はない」と語っているのを思い起こさせます。我々が日頃、欲しがっていたものを実際に手に入れてみると、期待したよりあっけなく拍子抜けしてしまったりするのも、もしかすると、欲望と快楽の独立性に原因があるのかもしれません。
さらにその先へ―悟りへの道?―
仏教の教えに、永続的な幸福を得ようとすることは、犬が自分の尻尾を追いかけるのと同様に無益である、というものがあります。つまり、幸福とは、はかない経験であり、長期にわたって持続するものではいということです。 実際に、幸福な経験は何度も体験するとその幸福感は色あせてしまい、次の幸福を見つけるための新たな経験を探し求めます。これは、新たな体験を得ることを可能にするための適確な手段に違いありません。 しかし、かつて自分を幸福にしてくれた経験が、繰り返しにより幸福感が薄れてきたとしても、その行動を引き続き繰り返すことがあります。われわれはこのような行動は中毒ではなく「習慣」と呼んでいます。
快楽を見つけ出したいという欲望を脳がどのように制御しているのか、そして、なぜ快楽が衰えるのかを理解することは、薬物中毒の治療のためだけでなく、私たち人間の情動を根本的に理解する上で極めて重要です。我々の研究は、人間が生きて行くための本質である快楽欲求(渇望:タンハー)を理解することに照準を定めており、まだ大部分が明らかにされていません。この未知の部分を明らかにするということが、我々にとってのタンハーであり、新たな発見は研究者のみならず人間を幸せにする物事のひとつなのです。